
世界に通じるクラフトビールへ。伊勢角屋麦酒と考える日本のビール文化の現在地
「日本のビール文化を、もっとおもしろくしたい」という信念のもと、個性豊かなビールを造ってきたキリンのクラフトビール事業『SPRING VALLEY BREWERY(以下SVB)』。
前回の記事では、SVBの新たな挑戦として、全国展開されているクラフトビール『SPRING VALLEY 豊潤<496>』の発売に至るまでの想いを開発担当の吉野が語りました。
これに続く企画として、『SPRING VALLEY 豊潤<496>』発売の背景にある、「もっとたくさんの方にクラフトビールを楽しんでもらいたい」という想いをより多くの人に届けるべく、クラフトビール文化の今とこれからを考える対談を実施することにしました。クラフトビール文化を盛り上げる全国各地のブルワリーにお話を伺っていきます。
今回は、地ビールブームの盛り上がりと衰退、そしてクラフトビール文化の発展を間近で見てきた「伊勢角屋麦酒」の社長・鈴木成宗さんをお迎えしました。異業種からビール醸造をはじめ、20年以上に渡る挑戦と改善により、今や世界的にも高く評価されるようになった日本を代表するブルワリーです。
対談するのは、キリンビールのマスターブリュワーを務める田山智広。日本のビール文化を見続けてきたふたりが、クラフトビールの現在地について語ります。
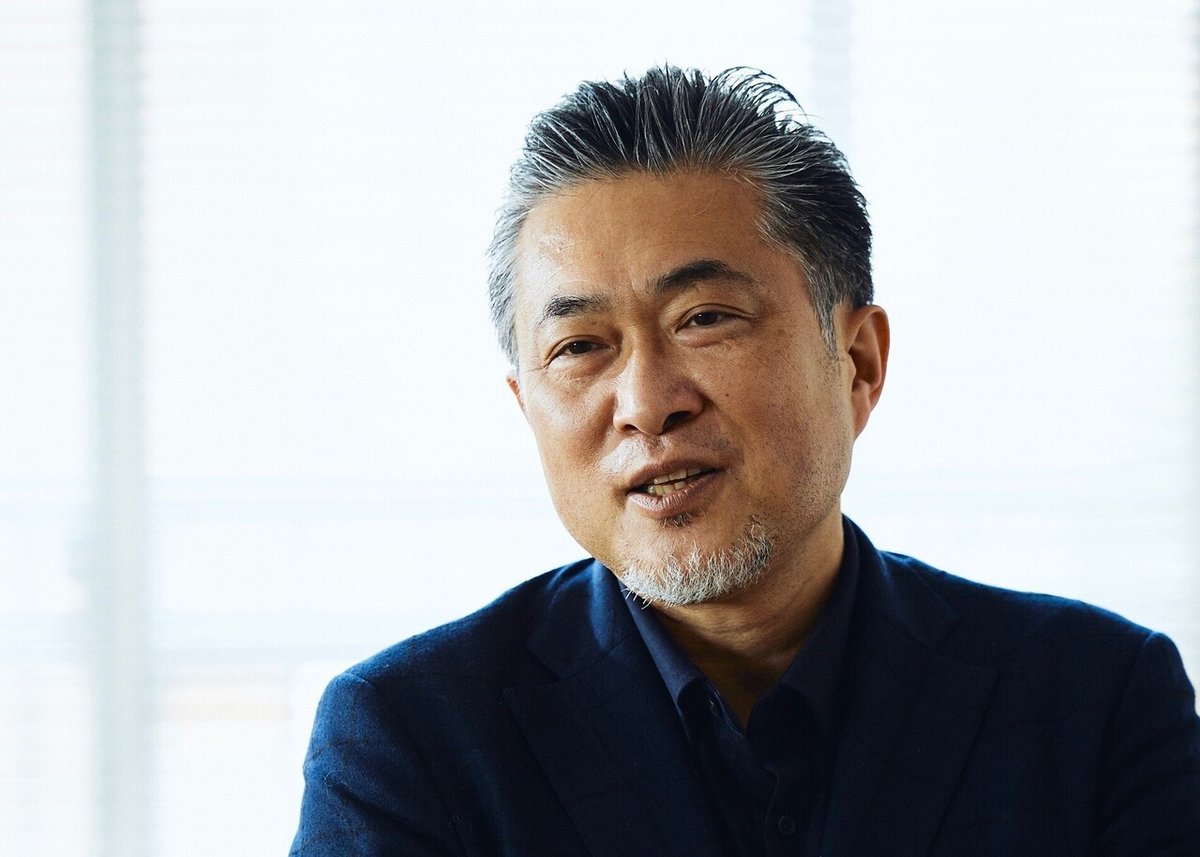
【プロフィール】鈴木 成宗
伊勢角屋麦酒 代表取締役社長
1967年伊勢市生まれ。東北大学農学部卒業後、20代続く「二軒茶屋餅角屋本店」を継ぐ。餅屋の仕事に就くも、大学時代に専攻した微生物の楽しさが忘れられず、1997年に地ビール製造販売とレストラン業を開始。日本企業初の「Australian International Beer Awards」金賞を受賞し、世界で最も歴史のあるビール大会で、「ペールエール」が2大会連続で金賞を獲得するなど、数多くの功績を残す。

【プロフィール】田山 智広
キリンビール株式会社マスターブリュワー
1987年キリンビールに入社。工場、R&D、ドイツ留学等を経て、2001年よりマーケティング部商品開発研究所にてビール類の中味開発に携わる。2013年から商品開発研究所所長、2016年4月からキリンビールのビール類・RTDなどの中味の総責任者“マスターブリュワー”に就任。今年リニューアルした「一番搾り」も監修。『SPRING VALLEY BREWERY』は企画立案より携わり、現在もマスターブリュワーとしてビールの企画開発を監修する。
知識も経験もないところからはじまった伊勢角屋麦酒のビール造り

─伊勢角屋さんは、お餅屋さんとして450年近い歴史があり、1923年からは味噌や醤油をつくる事業もされてきたそうですね。もともと鈴木さんは、家業のお餅屋さんを継がれていたんですか?
鈴木:そうです。大学卒業してすぐ実家に帰ってきて、餅屋の仕事を手伝いつつ、たまに味噌・醤油のほうも覗いていました。
─ビール造りをはじめられたのは1997年からということですが、そこにはどんなきっかけがあったのでしょうか?
鈴木:大学を卒業したら家を継ぐという約束をしていたんですけど、帰ってきたばかりの頃はまだ覚悟が決まっていませんでした。正直に言えば「仕方ないから帰ってきた」みたいな気持ちで。しかも、うちは典型的な家内制手工業で、父の個人商店のような感じだったので、そこに私がいても出る幕がないわけですよ。だから、エネルギーを持て余していたんです。
そんなときに、たまたま酒税法の規制緩和があって、小規模でもビールを造れるようになったんですよね。それを知って、「ひょっとしたら、これはおもしろいかもしれない。ビール造りなら、また酵母と遊べる!」と思ったのが最初のきっかけでした。
─もともと酵母が好きだったんですか?
鈴木:小さい頃から、なぜか微生物が大好きだったんです。天文も好きでしたが、たまたま望遠鏡よりも先に顕微鏡を買ってもらったからだと思うんですけど。日々顕微鏡を覗いているうちに、だんだんと微生物の世界にハマっていきました。
それと、ビール造りをはじめた理由として、世界ともっとつながりたいという想いがありました。うちで扱っているお餅は日持ちしないものですので、1日で届く範囲までしか商圏を広げられないんです。だけど、ビールだったらもっと遠くまで届けられると思ったんです。

─そうしてビール造りをはじめたということは、まったく知識や経験がないところからのスタートだったんですか?
鈴木:ほぼない状態ですね。味噌や醤油の発酵は見ていたのと、大学で生物系の勉強をしていたので微生物に対する最低限の知識はありましたけど、ビール造りに関してはまったくのド素人でした。
─そこからどのようにして、ビールを造りはじめたのでしょう?
鈴木:はじめは、三重県で最初にクラフトビールを造っていた「モクモク手作りファーム」さんに話を聞きにいくところからスタートしました。それから、兵庫県伊丹市の酒造メーカー「小西酒造」さんにお願いして、泊まり込みでビール造りを教えていただいて。あとはもう手当たり次第に文献を手に入れて、それを読みながらビール造りをしていましたね。
─最初に造ったのは、どんなビールだったんですか?
鈴木:ペールエール、バイツェン、スタウトの3種類です。当時は「地ビール」と呼んでいましたけど、そのなかでも典型的なものを三つ造ろうということで、フレーバーと色が違うものを選びました。
─それを地元で販売しはじめたと。
鈴木:そうですね。最初は地元で売り出して、飲んだ方の反応もよかったんです。でも、ホテルさんや飲食店さんに営業をしに行くと、「流行りにのった、老舗のバカ息子の遊びでしょ」って目で見られることがほとんどで。まともな商品としては見ていただけない感じでした。あの悲しさは、今でもよく覚えていますね。
─異業種からの参入という色眼鏡で見られてしまって、ビールそのものに目を向けてもらえなかったんですね。

─1997年というと、ちょうど日本各地で地ビールが登場してきた頃ですよね。当時のビールを取り巻く状況について、田山さんはどのように見られていましたか?
田山:僕は、1994年から1996年までドイツにいて、その間に日本で小規模のビール造りが解禁になったので、各地で地ビールが誕生しているのを遠くから見ている状態でした。帰国すると日本各地にブルワリーが立ち上がっていて、それはすごくいいことだなと思いましたね。もっと早くそういう時代にならないかなと思っていたくらいなので。各地に地ビールを飲みにいくという楽しみが増えたなと感じていました。
─実際に、田山さんも各地に足を運んで地ビールを飲まれていましたか?
田山:飲んでいましたよ。さまざまなビールがありましたが、その中には野心的なビールもあって、そういうチャレンジングな姿勢が眩しくも映っていましたね。
─ひとりのビールファンとして。
田山:そうですね。本当に純粋なビールファンとして、そういう状況を楽しんでいました。
ローカルに根ざしていることで生まれるグローバルな独自性

─伊勢角屋麦酒さんは「伊勢から世界へ」というビジョンを掲げられていますが、ビール造りをはじめた当初から世界に向けてという意識はあったんですか?
鈴木:ありましたね。先ほども申し上げた通り、ビール事業をはじめたモチベーションのひとつが、小さい世界に閉じこもらず、世界に出ていきたいというものでしたから。
それと、母方の祖父が伊勢神宮の人間だったので、神宮というものを身近に感じていまして。伊勢神宮には、式年遷宮のようなサステナビリティの精神だったり、同時にさまざまなものを受け入れる姿勢だったり、世界に通用するコンセプトを内包しているということもわかっていました。
つまり、“伊勢”そのものが世界に通用するブランドになると思っていたんですね。だから、「伊勢でビールを造る以上は世界の人に認められるものでなくてはならない」という気持ちは最初からありました。

伊勢角屋麦酒の主力6商品。左から『ペールエール』『ねこにひき』『ヒメホワイト』『IPA』『HAZY IPA』『XPA』。『ペールエール』は世界で最も歴史のあるビール大会「International Brewing Award」にて、二度金賞を受賞。
田山:今のお話にあったような「伊勢というローカリティーに根ざした上でのグローバルな視点」は、すごく重要だと思っていて。というのも、世界的に広がっているさまざまなビアスタイルも、結局はそういう背景を有しているんですよ。
例えば、「ヒューガルデン」というベルギーのビールは、もともと首都ブリュッセルの郊外にあるヒューガルデン村で飲まれていたローカルなビールでした。だけど、それが一度は廃れてしまったんですね。ただ、ローカルで長く飲み続けられてきたっていう事実は、クオリティの証なわけですよ。おいしかったから、日常に取り入れられて、長く飲み続けてこられたと。
そういった歴史に裏付けられたビアスタイルがのちに再発見されて、アメリカで「ヒューガルデン」にインスパイアされた白ビールが生まれたという流れがあったわけです。
田山:もともとはローカルで飲まれていたビールに、アメリカならではの原料を配合したりして、オリジナルのビールが誕生した。そういった流れが、クラフトビールが広がっていった過程だったりするわけですよね。だから、ローカリティがしっかりあって、そこが起点となってグローバル化していくことで、一つのカルチャーが生まれていく。それが今のクラフトビール文化が形成された流れなんです。

鈴木:視野が広くなればなるほど、ローカルの特異性って強くなると思うんですよ。例えば、三重県っていう単位で見たら、伊勢なんて別に大きな産業もない小さな町ですよ。でも、日本っていう単位で見れば、伊勢は天皇の祖先を祀る宗廟がある町ですし、世界という単位で見れば、自然と共存している唯一の聖地なんです。
そうやって視野が広くなればなるほど、伊勢の特異性はより際立ってくると思うんです。だから、我々が世界でビールをやっていこうと思えば思うほど、よりローカルの強みに光が当たってくるっていうのはありますね。
─実際に世界を目指していくための取り組みとして、伊勢角屋麦酒さんではどのようなことをされてきたのでしょうか?
鈴木:ビールに対して、世界の審査員がどういう評価をしているのかを学ぼうと思って、創業してすぐにクラフトビールの審査員資格を取りました。
─なるほど!世界ではどういうビールが評価されているかを知るために、審査員の資格を取られたと。
鈴木:そうですね。実際、世界的に大きな大会で審査員をやらせてもらったことで、「このビールを超えたら、世界の頂点が見えてくる」というのが実感としてわかってきたんです。
そこで感じた世界的なビールの潮流や評価軸を参考にしながら、一つずつ改善していくことを心がけてきました。いわゆるPDCAサイクルで、自分たちの造ったビールが世界一を獲れるかどうかという観点でチェックをして、そこまで至っていなければ次の仕込みで修正していくという。そういう愚直な改善を繰り返してきました。
─その結果、2003年には、世界4大大会の一つであるオーストラリアの「インターナショナル・ビア・アワード」で、日本企業初となる金賞を獲得されたと。受賞後には、周りからの評価も変わっていきましたか?
鈴木:もうガラッと変わりましたね。最初は相手にしてくれなかった営業先の方々も、「いや、おいしいと思ってたんです」って(笑)。それくらい大きな変化がありましたね。
豊かなビール文化を創造し、拡げていくために

─伊勢角屋麦酒さんは「豊かなビール文化を協創したい」という想いを掲げ、そのために同業他社の研修を受け入れたり、業界外とのコラボも積極的にされていますよね。そうやって、自分たちがおいしいビールを造るだけでなく、想いを同じくする人たちと共にビール文化を作っていこうという意識を持つようになったのは、なぜだったのでしょうか?
鈴木:私一人が田舎でやっていても産業にはならないですし、本当の意味で世の中には認められないじゃないですか。
ビールって非常にスタイルが多くて、クリエイティブなものだけに、お互いにすごくリスペクトしあえるんです。他のお酒ですと、目指す頂点が一つしかなかったりするじゃないですか。
―ひとつしかない椅子の取り合いになってしまいますよね。
鈴木:そうなんです。一つがトップで、あとは2位以下ってことになってしまいます。その点、ビールはスタイルで考えても100種類以上あって、お互いに違う頂上を目指せるのがいいんですよね。
そうやっていろんな山があって、そこからお客さまが好きなものを選べるというのが、クラフトビール文化にとって重要なことなんじゃないかなと。そういう状態を産業として作り上げていくには、文化を協創していくしかないと思ってるんです。

田山: その想いには、私も共感します。一社だけでできることって限られていますし、ビアスタイルだけでも100種類以上あるように、飲む人の好みも千差万別。同じものを万人が好きっていう状態は、むしろ不自然なわけですよ。いろんな個性があって、それぞれの好き嫌いがありますから。
私たちにも、好みやTPOに合わせてビールを選べて、それを楽しめるように、ビール市場を変えていきたいって想いがもともとあるんです。でもそれは、当然キリンだけじゃできなくて、業界全体で盛り上げていかないと、目指す将来像には至れないと思っています。
─もっと市場の選択肢を広げていこうと。
田山:そうですね。今のままだと、日本のビール市場はおもしろくないものになってしまうと思っているんです。選択肢が少ないという状況にしたのは、大手の責任でもあるので、自分たちの将来をしっかり支えるためにも、抜本的に構造を変えていかなければいけないんじゃないかなと。
そのためには大手としての力を発揮していく必要があるし、選択肢を広げていくことに共感してくれるブルワリーさんたちが一緒になってやってくれれば、我々としてもすごくうれしいなと思っています。

田山:自分たちが思い描いていた未来を実現させるためには、お客さんとクラフトビールの接点をさらに広げて、より多くの方に体感してもらうことが必要です。そういう状況のなかで、スーパーなどで日常的に買うことができる缶の商品を作るというのが、一つの方法としてあるんじゃないかなと思ったんです。そうしてたくさんの議論を重ねた上で発売したのが『SPRING VALLEY 豊潤<496>』だったんです。

田山: スーパーやコンビニで手に取りやすくなって、CMでも宣伝されるようになると、やはり「クラフトビール」の定義付けに対して賛否両論あります。だけど、きっかけは何であれ、興味を持っていただいて1回でも飲んでいただければ、これまでのビールとの違いを感じてもらえると思うんです。そこから100種類以上のスタイルがあって、さまざまな造り手がいるクラフトビールの世界に一人でも多くの方が入ってもらえたらなと。
鈴木:アメリカでも、クラフトビールの草創期には、その定義についてさまざまな激論が交わされていたんですよ。法廷闘争にもなったくらいで。論争が起きることで、注目が集まりますし、市場も活性化すると思うんですよね。ですから私は、キリンビールさんのような大手が、クラフトビール業界に一石を投じてもらって、そこから論争が起こるってことはウェルカムだと思うんです。
やはり、大手に対するアンチテーゼっていうのはクラフトビールの一つのコンセプトでもありますし。こういう議論は必要なんじゃないですかね。
クラフトビールという言葉の定義に対して論争が起きて、市場が盛り上がっているんだったら、それはいいことだと思っています。だって、興味がなかったら誰も論争なんてしないですからね。興味があるからこそ、気になっているからこそ、そこで論争が起きるわけなので。キリンさんとしては、クラフトビールをどのように定義しているのですか?
田山:キリンとしては、「造り手のパッションが感じられるビール」とか「創意工夫が感じられるビール」、「造り手の顔が見えるビール」というような表現をしていますね。伊勢角屋麦酒さんは、もともと地ビールとしてスタートされていて、今は「クラフトビール」という呼び方に変えていますよね。呼び方を変えたきっかけってあったんですか?

鈴木:ありました。最初は地ビール事業部という名称だったんですけど、2010年頃にクラフトビール事業部へと名称変更をしました。地ビールっていうと、どうしても「大手のマネをした二流品を、地場で造っている」というようなイメージがあったんですよ。でも、我々はそういうところではなく、世界を見据えたビールを造りたかったので、名称を変更しました。
─それによって何か変化はありましたか?
鈴木:社内のスタッフの目線が変わりましたね。地ビールというと、「伊勢のもの」ってところが力点になりますけど、クラフトビールである以上は世界標準でいいものを造っていきたいという意識に変わっていって。それは社内的によろこばれました。
規模拡大に伴うジレンマと、広くビールを届ける意義

─先ほど、クラフトビールにおける一つの価値観として、“大手に対するアンチテーゼ”というお話がありましたが、2018年に伊勢角屋麦酒さんが工場の規模を拡大した際にも葛藤はありましたか?
鈴木:自分の中にはありましたね。それまでは、ずっと手づくりで、モルトの香りを嗅いだり、ホップ入れて香りが変わる瞬間を確かめたり、本当に鍋で料理しているのと同じように造っていたんです。それを、規模を拡大してオートメーション化することに対して、私自身の抵抗感はありました。
未だに古いプラントに対する愛着はめちゃくちゃあって、ちょっと手が空いたら自分用のビールを造りたいと思っているくらいです。
─そういった抵抗があっても、規模を拡大しようと思った決め手は何だったんですか?
鈴木:旧プラントでは、1日に最大2,000リットルしか造れなかったんです。それを市場に出すと、ものの十数分で完売しちゃうような状態で。もはや市場に流通させることができないんですよね。
最初のうちは、たくさん売れるからよろこんでいたんです。でも、どんどん“買えないビール”になってしまって、そのうち市場から苦情が入りはじめたんですよね。「本当にうちに買ってもらう気ある?」って。

鈴木:ありがたいことに売れてはいたので、そのままでも向こう何年かは安泰だったと思うんです。でも、このままでは最初に自分が思い描いていたような、「いろんなクラフトビールが手に取れるようになったらいいな」というところには絶対に辿り着けないと思って。
立ち上げ当初は、「伊勢から世界に」と思っていたのに、世界はおろか国内で売るビールもない状態で終わりたくなかったんです。
─ほしい人に届かないという歯痒い状況だったんですね。
鈴木:そうなんです。そうすると、自分たちだけの商売になっちゃって、文化にはなっていかないなと思ったんですよね。

田山:これは、すごく本質的な話だと思うんですよ。日本のクラフトビール市場は、スケールアップのスピードが上がっていかないっていう。
私も、鈴木さんが規模を拡大するって聞いたときに、「あぁ、よかった」と思ったんです。アメリカは「いつかは会社を大きくしてやるぞ」ってみんな野心的にチャレンジしますが、日本の場合は必ずしもそうでもないんですよね。それもたしかに一つの在り方だとは思うんですけど、「せっかく世界に誇れる素晴らしいビールを造っているのにな」と思うこともあって。
鈴木:スタートアップのブルワリーって、万が一失敗した場合に、あらゆる資産を失って再起できなくなっちゃうっていうのもハードルを高くしているんだと思います。
田山:だから最近は、クラウドファンディングなどを上手く使って拡張しているブルワリーさんも増えてきていますよね。
伊勢角屋麦酒さんをはじめ、拡張に成功したブルワリーを、みんなが見ていると思うんですよ。それで機運が変わって、日本のクラフトビールが正のスパイラルに向かっていけばいいなと思っています。
目指すは世界に通じる日本のクラフトビール

─鈴木さんは今後、日本のビール文化がどのようになっていってほしいと思っていますか?
鈴木:やっぱり海外と同じように、いろんなビールを、個人の判断で手に取れるようになっていくのが理想だと思っています。私は、そこをずっと夢見てきたので。
あとは、「これがジャパニーズスタイルのビールだ」という、世界に通用するビアスタイルを造りたいですよね。例えば、海外には、「ウェストコーストスタイル〇〇」とか、「ベルジャンスタイル〇〇」といったビールがあるじゃないですか。でも、「これぞ日本だ」っていう、世界を席巻するビールはまだ出てきてないので。そういうものを造っていきたいなと思っています。
─おぉ、それは楽しみです!
鈴木:いろいろやり方はあると思っているんですけど、今はなかなか自分の時間を開発に向けられないので。社長業って、割と忙しいんですよね。「ビールを造りたくてはじめたのに、全然造れてないじゃないか!」って思っています(笑)。
─やっぱり今も、現場でビール造りたいっていう気持ちは強いんですか?
鈴木:はい。かなり強いですね。それが一番楽しいですもん!社長業がメインですが、頭のなかには常に新しいビールのイメージがあります。単にビールと向き合っているだけではなく、日本のいろんな暮らし方や食文化、建築なんかもそうですし、そういうさまざまなものにインスパイアされて、日本らしいビールが生まれてくると思うんですよね。
そういった意味では、伊勢という土地はとても恵まれていると思います。古くから続く神道文化がありますし、海、山、里の食べ物は大抵なんでもありますから。
─「日本らしいもの」を造るうえでは、すごくいい土地なんですね。

─田山さんは、いかがですか?今後、日本のビール文化について、何か思っていることがあれば聞かせてください。
田山:今の鈴木さんのお話にまったく同意です。やっぱり日本ならではのクラフトビールを造りたいなと。今、クラフトビールを飲むために日本に行きたいって人がどれだけいるかというと、ほとんどいないと思うんですよね。でも、ポートランドにクラフトビールを飲みに行く人はいるじゃないですか。そういうふうに、日本のクラフトビールを飲みたいから、日本に行くってことになっていけばいいなと思っています。
そのためにはやっぱり、日本オリジナルのビアスタイルを含めて、日本じゃないと飲めない、本当においしいビールが出てくるってことが前提ですよね。そうやって日本ならではのビールを造っているブルワリーさんがたくさん出てくるといいなと思っています。
─素材や製法や生産地など、様々な要素があると思いますが、オリジナルのビアスタイルって、どうやって生まれてくるものなんですかね?
田山:最近は、日本酒の酵母を使ったり、柚子を使ったりしたビールも出てきていますよね。だけど、単に日本の素材を使うだけでなく、そこにブリュワーのクリエイティビティが入ることで新しいものが生まれてくるんじゃないかなと思います。
日本の食文化でいうと、和食ってやっぱり独自の世界観があるじゃないですか。同じ種類の魚を使ったとしても、イタリアンと和食では違う料理になりますよね。やっぱり日本独特の感性が入ることで、ユニークな視点が出てくるんだと思います。そういうことを、ビールの世界でもできるんじゃないかなって。
─なるほど。そう言われてみると、たしかにビールにも日本の独自性というのは反映できそうですね。
田山:日本の繊細な食文化にマッチするようなビールとかね。食とのセットで考えていくと、いろんな可能性があると思うんですよ。きっと、これからはそういうビールが生まれてくると思うし、僕らもそこを目指していきたいと考えています。
─そういうふうに考えると、今、日本のクラフトビールはすごくおもしろい時期にいるんですかね。新しいものが生まれかけているタイミングというか。
鈴木:面白い時期の直前かなと、私は思っていますけどね。
─夜明け前のような。
鈴木:うん、もしかしたら一番暗いところかもしれないですね(笑)。
田山:あはは。是非とも、明るい夜明けを迎えたいですね(笑)。
***
地ビールの発展・衰退を経て、さまざまな論争を繰り広げながら、進化を続けるクラフトビール界。今後、日本の独自性を反映した新しいビールは生まれてくるのでしょうか。
伊勢角屋麦酒も、「伊勢から世界に」という想いのもと、さらなる高みを目指して世界に向けた新しい挑戦を続けています。
次回のゲストは、浦安市舞浜の商業施設「イクスピアリ」に「ハーヴェスト・ムーン」を立ち上げ、日々多彩なビールを造り続ける園田智子さん。ビール造りにかける情熱やクラフトマンシップについて、キリンマスターブリュワー田山智広、『SPRING VALLEY 豊潤<496>』の中味開発を手がけた山口とともにお話ししていただきます。


